🧠 ノイマン型コンピュータとは?
✅ ざっくり言うと…
プログラムをメモリに入れておいて、それを順番に実行するコンピュータの仕組みのこと
現在使われているパソコン・スマホ・サーバなど、ほとんどすべてのコンピュータはこの仕組みが使われている。
❓ 「ノイマン」って?
ノイマンさんという科学者が、昔「こうすればコンピュータって効率的に動くよね」って考えて、提案した設計モデルのことを「ノイマン型」って呼ぶようになった、らしい
🧩 ノイマン型コンピュータの3つの特徴
| 特徴 | 内容 | イメージ |
|---|---|---|
| 1. プログラム内蔵方式 | プログラム(命令)もデータも、どちらも同じ場所(メモリ)に入れておこう!という考え方 | 「『やることリスト』と『材料メモ』を同じノートに書いておこう」 |
| 2. プログラムの順次実行 | 命令は上から順番に、1個ずつ実行していく | レシピ通りに1手順ずつ進める |
| 3. 一元的な記憶装置 | プログラムもデータも、同じ記憶装置(メモリ)に保存するという構造・仕組み | プログラム用とデータ用のノートが分かれてない状態 |
🔄 処理の流れ(ざっくり)
- 入力装置から情報を受け取る(例:数字を打ち込む)
- プログラム(計算方法)と一緒に、メモリに保存
- CPUがプログラムを読んで、演算処理をする
- 結果を出力装置に表示(例:画面に数字を出す)
👉 この流れがあるのが「ノイマン型」の特徴でもある
📝 まとめ
ノイマン型=プログラムもデータもメモリに一緒に入れて、順番に読んで処理してくれるもの
ちょこっと補足
①プログラム内蔵方式という考え方が生まれた背景
- それまでのコンピュータは、「計算方法(プログラム)」を外から毎回設定しないといけなかった。
- ノイマンさん 「プログラムもデータと同じようにメモリに入れておけばよくない?」
⇒そんな感じでプログラム内蔵方式を持つノイマン型コンピュータが開発された!
②ノイマン型の弱点
プログラムもデータもメモリで管理することで、1本の通路でやり取りするから処理が詰まる
⇒処理速度が遅くなる

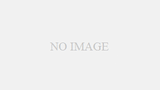
コメント