◆ ハードディスクの内部構造
ハードディスク(HDD)の中には、以下のような部品が入っている。
- プラッタ(ディスク)
金属やガラスの円盤。データはここに磁気で記録される。1台に複数枚入っていることも。 - アクセスアーム
磁気ヘッドをディスクの目的の場所に移動させるためのアーム。 - 磁気ヘッド
プラッタの上をすれすれに浮かびながら、高速回転するディスクから情報を読み取ったり書き込んだりするパーツ。
プラッタは毎分数千回転とかいうすごいスピードで回転しており、これらが連動して動くことで、ハードディスクは「データの読み書き」を実現している。
◆ プラッタ内の領域構造
プラッタの中は、以下のような階層構造でデータを管理している。
- セクタ(Sector)
プラッタ上を扇状に分けた最小単位。 - トラック(Track)
プラッタを一周した円形のデータの列。複数のセクタが並んで構成される。 - シリンダ(Cylinder)
同じ位置にある複数のトラック(複数のプラッタにまたがる)をまとめたもの。
イメージとしては、玉ねぎの輪のような「トラック」が何層にも積み重なっていて、それを串刺しにしているのが「シリンダ」といった感じ。
◆ クラスタとは?
OS(Windowsなど)がデータを読み書きする際は、「セクタ」ではなく「クラスタ」という単位で処理する。
これは小さすぎる単位でアクセスするとかえって非効率になるためで、
例えば「8セクタをまとめて1クラスタ」といった具合に設定されており、読み書きの効率を高めている。

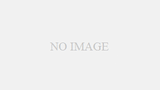
コメント